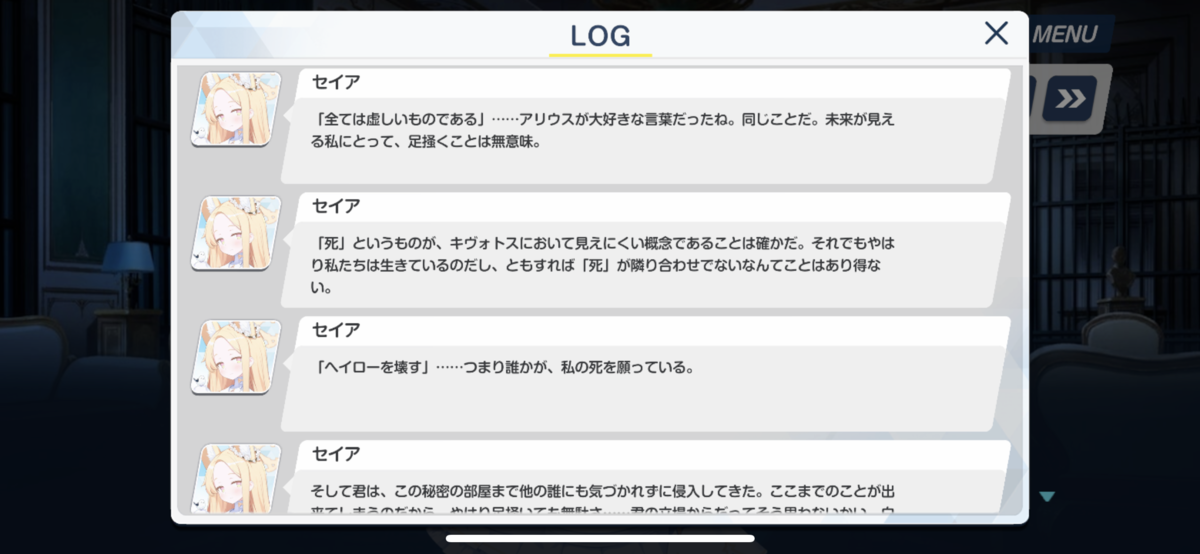
『ブルーアーカイブ』の「エデン条約編」はかなりメタフィクション的です。
ただし、メタフィクションといっても、あくまで物語に埋めこまれ、隠れたものです。
でないと、中学生が考えたようなシナリオになってしまいます(「サービス終了したソーシャルゲームのキャラクターたちが世界の終末を旅する」とか、そういうのです)。
さて、「エデン条約編」を通じてキーワードとなるのが、「キヴォトスの『七つの古則』」の「五つ目の古則」です。
"セイア「キヴォトスの、『七つの古則』はご存知かい?
その五つ目は、正に『楽園』に関する質問だったね。
『楽園に辿り着きし者の真実を、証明することはできるのか』/
他の古則もまたそうであるように、少々理解に困る言葉の羅列だ。
ただ、一つの解釈としては、これを『楽園の存在証明に対するパラドックス』であると見ることができる。/
もし楽園というものが存在するのならば、
そこに辿り着いた者は、至上の満足と喜びを抱くが故に、永遠に楽園の外に出ることはない。/
もし楽園の外に出たのであれば、つまりそこは真の悦楽を得られるような『本当の楽園』ではなかったということだ。
であるならば、楽園に到達した者が、楽園の外で観測されることはない。存在を捕捉されうるはずがない。/
存在しない者の真実を証明することはできるのか?
つまるところ……この五つ目の古則は、初めから証明することができないことに関する『不可解な問い』なのだよ。/
しかしここで同時に、思う事がある。証明できない真実は無価値だろうか?
この冷笑にも近い文章を通じて、何か真に問いたいことがあるのではないだろうか?/
エデン……経典に出てくる楽園(パラダイス)。どこにも存在せず、探すことも能わぬ場所。
夢想家たちが描く、甘い甘い虚像。/
どうだい? そう聞いてみると、この『エデン条約』そのものが、まさしくそんなもののように思えてこないかい?」"
(第1章第1話「プロローグ」)
「五つ目の古則」の「楽園」は、あきらかに『創世記』の失楽園のエピソードを示しています。
じつは、『創世記』の失楽園のエピソードは、メタフィクションでしばしば用いられるものです。
有名なところでは、ポール・オースターの『ガラスの街』があります。
"エデンにおけるアダムの唯一の仕事は、言語を創り出すこと、生き物や事物それぞれに名前を与えることであった。その無垢の状態にあって、彼の舌は世界の核にまっすぐ届いていた。言葉は彼が見たものに付随するだけでなく、それらのものの本質を明かし、文字どおり生命を吹き込んだ。物と名は交換可能であった。堕落後はもはやそうではなくなった。名は物から隔たり、言葉は無根拠な記号の集まりになり果て、言語は神から切り離された。ゆえに楽園の物語とは、人類の堕落のみならず、言語の堕落を伝える物語でもあるのだ。"
『創世記』の失楽園のエピソードが、メタフィクションでしばしば用いられるのは、これがアダムの言語に関わるからです。
アダムの言語とは原初の言語、普遍言語のことです。
なぜ、普遍言語がメタフィクションで重要視されるかというと、もし普遍言語が存在するなら、概念と実在がかならず対応することになるからです。
フィクションで、概念と実在が対応しないと困る理由はわかりますね。ルイズコピペや"「惣流・アスカ・ラングレー」「これは単なる絵だ」"のようなことになってしまうからです。
しかも、普遍言語の問題は、現代まで脈々と続いています。
パオロ・ロッシの『普遍の鍵』と、ウンベルト・エーコの『完全言語の探求』によると、おおまかに以下のような歴史になります。
先駆的に、ヤコブ・ベーメがバベルより以前の自然言語(ナチュル・スプラキ)を提唱。
コメニウスが記号と事物との対応の問題を提起。論理学と百科全書に発展。
ライプニッツが普遍記号法を研究。現代に至る。と、いうことです。
さて、哲学者のドナルド・デイヴィドソンは『真理と解釈』所収の論文「真理と意味」で、こうした問題に決着をつけます。
すこし遠回りになりますが、「真理と意味」の内容を説明します。
デイヴィドソンは、フレーゲの論理学による普遍言語の試みを批判します。
フレーゲはすべての文に対象を与えようとしました。ですが、「アネットの父」の「の父」は無限につけ足すことができて、これにはあきらかに対象がありません。
また、文の意味は指示だと見なしました。ですが、これだと同じ事物を指示するすべての文は同じ意味だということになります。そんなはずはありません。
デイヴィドソンは、「t(名辞)がx(独立変項)を指示する」という形式の文すべてが意味をもてればいいとしました。個々の語についても、文が意味をもつだけの意味があればいいということです。
また、意味は「s(文)がm(文の意味を指示する名辞)を意味する」という形式の文すべてを帰結としてもてばいいとしました。
こう考えれば、意味は指示を兼ねるので、対象を想定しなくてもいいわけです。
ある文の意味は、その言語のすべての文の意味を与えれば、与えられることになります。
これは言いかえれば、「s(文)はthat p(pということ)を意味する」となります。
この「を意味する」は、次のように言いかえれば、消去できます。
「sがTであるのは、pの場合、かつその場合に限る」。
以上から、ある言語に関する意味とは、すべての文を含意するだけの制約を述語「Tである」に与えることだといえます。
おわかりでしょうが、「Tである」は「真である」です。
こうして、意味については意味を使わず、真理(真か偽か)だけですべてを表わせるわけです。真理が何かは、文が加わるたびに変わっていきます。
(冗長になるので言及しませんが、クワインの『ことばと対象』は『真理と解釈』とたがいに補っていて、参考になります)
こうして、普遍言語の問題は決着がつきました。
ですが、これは失楽園でもありました。
概念と実在の、唯一で絶対の結びつきを絶つことでもあったからです。
「エデン条約編」での、聖園ミカの裏切りも、こうして可能になるわけです。
いうまでもなく、『ブルーアーカイブ』のシナリオはひとつの文です。
「最終章」では、ゴルコンダがメタフィクション的に「テクスト」と言ってさえいます。
ミカの裏切りとは、裏切り行為というより、むしろキャラクターの変化ということです。
もちろん、いまはミカについては、「もう夜遅いから返信はしなくていいよ。おやすみ」というモモトークがきたら、誰でも危険信号が点いたと考えるキャラクターです。
ですが、「エデン条約編」の第2章「不可能な証明」までは、その言葉を文字どおりに受けとっていいキャラクターでした。文字どおりに受けとって寝たら、翌朝には未読が50件くらい溜まっていそうなキャラクターではありませんでした。
このことは、言語についてだけでなく、現実の心理についても当てはまります。
"ハナコ「……いえ、先生が仰りたいことは――/
私たちにはミカさんの本心を察することなどできない……そういうことですか?」
〈「楽園に辿り着きし者の真実を、証明することはできるのか」……〉
ハナコ「五つ目の……/
楽園に辿り着いた者は、楽園の外で観測されることが無い。存在することを観測できない……楽園の存在証明に関するパラドックス……」
〈……証明できないものを、どう証明するのか。〉
ハナコ「……。
もし「他者の本心」なんてものに辿り着いたら……それはもう、他人ではありません。/
辿り着けないなら、やはり本心など分かっていないということで……。/
楽園も、誰かの本心も一緒……そういうことですか?/
……確かに、そうかもしれませんね。私たちは誰かの心に直に触れる方法も、その真実を証明する術も持ってはいません。/
「誰かの本心を理解した(楽園に辿り着いた)」という言葉を、どうすれば「本当」だと証明することができるのか……/
正に矛盾……不可能なのでしょうか。他者の本心を理解する方法は、無いのでしょうか……。」
〈……無いんだろうね、きっと。〉
ハナコ「……。」
〈それはきっと、不可能な証明……。/
……だとすればもう、信じるしかないのかもしれない。/
そこには楽園がある、って。〉
ハナコ「……。/
そう、ですね……。/
考えてみれば、先生は最初からそうでしたね。この疑惑と疑念で満ち溢れたお話の、初めからずっと――」"
(第3章第3話「ポストモーテム(3)」)
デヴィッドソンは『行為と出来事』所収の論文「行為・理由・原因」で、ひとの行為の意図は、理由というより原因だといいます。
理由については、このように定式化できます。
「記述d、行為Aについて、理由Rであるのは、以下の場合、かつその場合に限る。RはAに対する賛成的態度と、Aのdに関する信念である」。
ただし、理由はつねに複数考えられます。なので、行為と意図については因果性が必要で、意図は理由というより原因だということです。
そして、同書所収の論文「心的出来事」で、心理について述べます。
態度と信念が意味をなす、または、行為を記述するときは、行為と信念と欲求に最大限の合理性と整合性を想定しなければならない。これは言語行為を解釈するときと同じである。と、いうことです。
こうして、テクストのキャラクターと、現実の人間が同じ問題でとらえられます。
このことは、逆説的に、作品がフィクションであることをユーザーに意識させます。つまり、メタフィクション的になります。
そのことを象徴するのが、「エデン条約編」でキーパーソンとなる百合園セイアです。
セイアは予知能力をもち、時間を超越して、作中のすべての出来事を知る立場にいます。そして、そのすべての出来事は変えることができません。
つまり、セイアはユーザーと同じ立場にいます。
また、セイアはキヴォトスにおいて死は見えにくい概念だと言います。そして、その例外がヘイローを破壊することだと言います。
これは、そのままソーシャルゲームのキャラクターのことだといっていいでしょう。
例外的な死とは、シナリオにおける死や、システム上での抹消のことだといえます。
ただ、キヴォトスにおける生死については、秤アツコの絆エピソードで言及があります。
アツコが"「子どもって、どうやってできるの?」"と尋ね、「先生」が慌てふためくというものです。
これによると、キヴォトスにおける生殖も現実と同じものということになります。
もっとも、アツコの脱いだ蒸れたレオタードの周りで「先生」が三日三晩踊りあかせば、そのなかから生命が誕生するという仕組みだったりするのかもしれません。だとすると、「先生」が言葉を濁すのも当然です。
セイアはキヴォトスでは「約束」が重要だと言います。
これは、作品ではテクストそのものは無視できないことだといっていいでしょう。
一度テクストにしたものは、制作者の過誤や都合で無かったことにはできないということです。
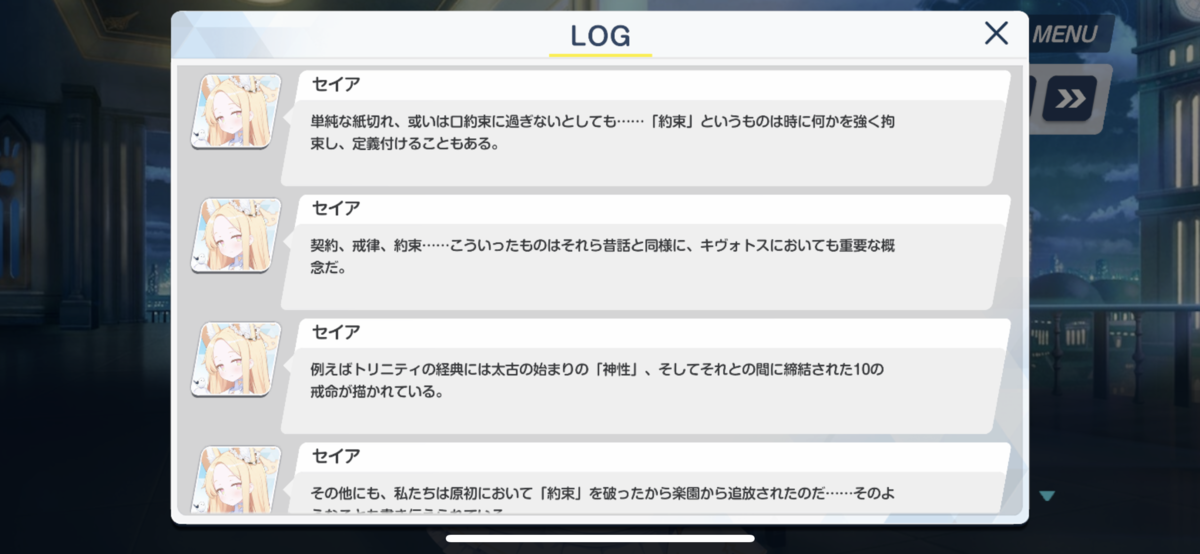
"セイア「先生、君はキヴォトスの外部から来た人間であり大人だ。となれば、契約、取引……そういった「約束事」のもつ重要性についてよく知っていることだろう。/
たとえば「悪魔と契約する」、という言い回しがあるだろう?/
昔話においても「驚異的な何かが不注意な約束をしてしまったがために敗北する」、あるいは逆に「そういった約束によって打ち勝つ』というお話は幾つもある。/
……だけど、そこからはこうも読み取れないかい?/
単純な紙切れ、あるいは口約束に過ぎないとしても……「約束」というものは時に何かを強く拘束し、定義付けることもある。/
契約、戒律、約束……こういったものはそれら昔話と同様に、キヴォトスにおいても重要な概念だ。/
例えばトリニティの経典には太古の始まりの「神性」、そしてそれとの間に締結された10の戒名が描かれている。/
その他にも、私たちは原初において「約束」を破ったから楽園から追放されたのだ……そのようなことも書き伝えられている。/
……今さらな話かな。なにせ実際に君は、そういった概念を利用した誰かを救ったことがあったはずだ。」"
(第3章第10話「甘い嘘」)
こうして、「エデン条約編」は『ブルーアーカイブ』という作品そのものの是非を問うものになります。
そのことは、プロローグであらかじめ述べられます。
"セイア「もしかしたらこれから始まる話は、君のような者には適さない、似つかわしくない話かもしれない。/
不快で、不愉快で、忌まわしく、眉を顰めるような……/
相手を疑い、前提を疑い、思い込みを疑い、真実を疑うような……/
悲しくて、苦くて、憂鬱になるような……それでいて、ただただ後味だけが苦い……そんな話だ。/
しかし同時に、紛れもない真実の話でもある。/
どうか背を向けず、目を背けず……最後のその時まで、しっかり見ていてほしい。」"
(第1章第1話「プロローグ」)
さて、では、その答えはどのようなものでしょう。
それは、ただ信じるというだけのことです。

"セイア「……。/
これが全ての、無意味な足掻きの終着点……。/
私はアズサに警告をしていた。何度も何度も、このような結末になるだろうということを。/
それでもアズサは、希望を抱いてしまった。淡い希望を。/
……。
だから言っただろう?/
これが物語の結末。何もかもが虚しく、全てが破局へと至るエンディング。ここから先を見たところで、無意味な苦痛が連なっていくだけだ。/
これはつまるところ各位が追い詰められ、結局誰かが誰かを殺める物語。誰かが、人殺しにならざるを得ない話。/
不快で、不愉快で、忌まわしく、眉を顰めたくなるお話だ。/
悲しくて、苦くて、憂鬱になるような。それでいて、ただただ後味だけが苦いお話……そうは思わないかい。/
しかし同時に、紛れもない真実の話でもある……。/
これが、この物語の正体だ。/
……。/
君は以前、五つ目の古則に対してこう言っていたね。/
「ただ楽園があると信じるしかない」、と。/
然して、信じた結果がこれだ。/
元より不可能だったのだよ。エデン条約、お互いに「憎み合うのはやめよう」という約束。/
そんなこと、できるはずが無いというのに……。/
その上、条約の名前に「エデン」と来た。ここで楽園の名前だなんて、相変わらず連邦生徒会長の不愉快な冗談は皮肉にもほどがある。下手をすれば悪意すら感じてしまいそうなほどだ。/
このプロセスを経て、確認できたものはあるだろう。/
それは不信から降り積もった、ゲヘナとトリニティの互いへの恨み。そしてアリウスたちが持つ恨み。/
それらを通じてこの条約は、歪な形で完成されてしまった。
何よりも皮肉なことに、何処にも存在しない、証明すら出来ない……その楽園の名前を携えて。/
まさに、楽園から追放された私たちに相応しい結末なのかもしれないね。」"
"セイア「……先生。君は未だに、楽園を信じているのかい?/
証明すらできないまま、ただ盲目的に信じていると?/
「楽園に辿り着きし者の真実を、照明することはできるのか」……
つまりこれは楽園証明の話ではなく、ただそれを信じられるかという話だとでも……?」"
(第3章第15話「五つ目の古則への答え」)
信じるというと聞こえは良いですが、実際にはそれしかできないので、消極的なことです。
デイヴィドソンは『真理と解釈』で、解釈は「慈善の原理(プリンシプル・オブ・チャリティー)」を前提にしなければならないと述べます。
文は発話者に最大限の合理性と整合性を想定しなければ、解釈できないということです。
「慈善の原理」というと聞こえが良いので、最近は「チャリタブル・リーディング」などという新語もつくられたりしています。
ですが、「慈善の原理」はあくまで最大限の合理性と整合性を想定するものです。ですので、発話者に悪意があったり、愚かさがあったりすることを想定することさえ含みます。
「チャリタブル・リーディング」などと言うひとは、それ以前に正確にリーディングしたほうがいいでしょう。
仮に、「慈善の原理」に倫理的な含意を見出すなら、それは発話者における理由を尊重することでしょう。「チャリタブル」などと言って、解釈者に都合のいい理由を発話者に押しつけることは、「慈善の原理」の真逆です。「チャリタブル」などと言うひとは、どれだけ「チャリタブル」に解釈しても愚かです。
さて、「エデン条約編」の最後で「先生」は信じるという消極的なことをおこないます。
ですが、その結果は知ってのとおりです。
まさに予想外の展開である、阿慈谷ヒフミによる『ブルーアーカイブ』のタイトル回収です。
これはそれまでのテクストからして、予想外でありながら、きわめて妥当なものです。
ですので、ユーザーも感動します。
信じるという、それだけしかできない、消極的なことの価値を知らしめる『ブルーアーカイブ』の「エデン条約編」は、優れたフィクションであり、またメタフィクションだといえます。
最後に、楽園と、楽園としての文学について、ニコール・クラウス著、広瀬恭子訳『フォレスト・ダーク』から引用します。
"楽園からの追放は、その主たる点において永遠である。したがって楽園からの追放は決定的であり、この世での生は逃れようがないが、それにもかかわらずその過程の永遠性ゆえに、我々は永久に楽園にとどまりつづけることが可能になったばかりか、現にいまも楽園にいるということもありうるのだ。この世の我々がそれを自覚していようといまいと。
――カフカ"(『フォレスト・ダーク』巻頭言)
"けれど楽園追放は、カフカの理解では、生命の木の実を食べなかった(、、、、、、)せいなのだ。あの庭の真ん中に立っていたもう一方の木の実を食べていたら、目覚めたわたしたちの体内には永遠が、カフカが「不滅のもの」と呼んだ存在が宿っていたはずだった。いまや人は誰しも善悪を見分ける力においては基本的に対等だとカフカは言う。差が出るのはその知恵を得たあと、それに従って各々が動く努力しなければいけないところからだ。それなのにわたしたちには善悪の判断に従って動く力が足りないためにあらゆる努力は無に帰し、しまいにはその努力で身を滅ぼすだけになりかねない。エデンの園であの実を食べたことで身についた知恵をなかったことにしたいだけなのに、それができないばかりに正当化を図り、そうしたら今度は世界に正当化が溢れかえることになった。「ひょっとしたら現世そのものが」とカフカは思いをめぐらせる。「束の間の休息を求める人間の自己正当化以外のなにものでもないのかもしれない」。どうやって休息を得るのか? 知恵それ自体が目的になりうると思いこむことでだ。その間、アダムとイヴが致命的に生命の木を見落としたのとまったく同じように、わたしたちは自分たちの内にある永遠を、不滅のものを見落としつづける。永遠がそこに、いつでも自分の内にあって、上に向かって枝を伸ばし光の下で葉を広げていると信じていなければ生きていられないくせに、見落としつづけるのだ。そういう意味では、楽園とこの世界とのあいだのとば口など錯覚なのかもしれず、じつはわたしたちは楽園を離れたことなどないのかもしれないとカフカはほのめかす。そういう意味では、わたしたちはいまこの瞬間ですらも、そうとは知らず楽園にいるのかもしれないのだ。"(『フォレスト・ダーク』p.286)
ちなみに、『フォレスト・ダーク』にはヘイローについての記述もあります。
"リビングでスイッチに手を触れると、自動調光機能つきの室内灯が目を覚まし、東側の壁に一つだけかかっている小さなパネル画の表面に、つやのある金色の光輪が二つ浮かびあがった。幾度となく見てきた光景だが、その効果を目にするたび、頭皮がそくっとする。それは唯一手もとに残してある傑作で、六百年近く前にフィレンツェで描かれた祭壇飾り用のパネル画だ。(中略)
……二人の頭のまわりの平らな金色の円盤だけが、奇妙に静止している。なぜ当時は光輪をこんなふうに描くことにこだわったのだろう。奥行きの錯覚の生み出し方を発見したあとでもなお、これについてだけは執拗な平面性に常に立ち戻ったのはなぜか。しかもそれがなんでもよかったわけでなく、神の近くに引き寄せられ、無限によって満たされるものの象徴にほかならなかったのは?"(『フォレスト・ダーク』pp.44-5)
ここまで読まれたかたなら、この修辞疑問文の答えはもうおわかりでしょう。もちろん、ヘイローを描き忘れないためです。
ついでに、『ブルーアーカイブ』の「最終章」についても触れます。
「最終章」は、より直接的にメタフィクション的です。さまざまな用語が登場します。
ですが、「エデン条約編」で問題になった、概念と実在という区分に当てはめれば、理解するのは簡単です。
「最終章」から登場する用語で中心になるのは「崇高」と「色彩」です。
「崇高」は、美学論であるカントの『判断力批判』で扱われる概念です。
カントは人間の認識能力を理性、悟性、判断力に区分しました。ここで重要になるのが、超越論という概念です。超越論は論理学や数学といった、普遍的な法則のことです。
もうおわかりでしょうが、超越論には直接的には触れることができません。失楽園です。実際、『純粋理性批判』では、理性だけによる「恩寵の王国」というユートピアが仮定されています。
ですが、美感に近い判断力では、超越論的なものにほぼ触れることがあります。そのときの感覚が「崇高」です。
ゲマトリアは「崇高」を目指しています。
超越論的なものは上位の次元にあるといえます。
つまり、作中世界で「崇高」を目指すとは、フィクションの力を使って、メタフィクション的に現実世界を目指すということでしょう。
(リオタールの『崇高の分析論』はこのことを詳しく述べています)
「色彩」についても、『判断力批判』に「色」は「魅力」だという論点があります。
「美」は形式であって、色は形式に注意をうながすためのだけのものであり、「魅力」であって「美」ではないといいます。
一方で、やはり「美」ではない「崇高」とは、ある意味で近いともいいます。
メニングハウスの『吐き気』は『判断力批判』を分析しています。
それによれば、理性、悟性、構想力が、それぞれ「崇高」、「美」、「吐き気と羞恥心」に対応するそうです。ここでは、判断力と構想力は区別しなくてもいいです。「吐き気と羞恥心」は「魅力」と同類とみていいでしょう。
つまり、作中世界での「色彩」は、「崇高」とは別の方法で現実世界を侵蝕するものだといっていいでしょう。
例えば、エログロです。
つまり、「色彩」はエロ二次創作のたぐいだということです。
このことを考えれば、ゲマトリアが「色彩」に恐怖し、敵意を抱くこともわかります。
冗長になるのでいちいち説明しませんが、その他の用語も同じように整理できます。
また、最終章が『ブルーアーカイブ』のプロローグに繋がり、アロナが失踪した連邦生徒会長だったと明かされる物語の円環構造も、同じように解釈できます。
「先生」、すなわちプレイヤーを作中世界に招来させ、物自体であるテキストを、悟性をもって認識させる。それにより、作中世界を「実在」化させる。それが連邦生徒会長の目的だったということでしょう。
つまり、ジーン・ウルフの『デス博士の島』タイプのメタフィクションだということです。